フレームの〈型〉 vs 現場の〈成果〉を対比で読み解く
形は作れる。だが、成果は別物。――このギャップを埋める3つの鍛え方を、具体例と対比で解説します。
この記事でわかること
- 見かけの容易さ vs 実際の難しさ
- フレームワークがくれるもの vs くれないもの
- 良い戦略の「核」 vs ありがちな落とし穴
- 鍛え方(3つ):思考の型/小さく試す/実行OS
導入:なぜ「戦略は簡単そう」に見えるのか vs それでも難しい本当の理由
- 簡単そうに見える側
- 汎用フレーム(5フォース、SWOT、BMC)で“形”はすぐ整う
- 成果は数か月〜数年後に出るため、短期は自己評価が甘くなる
- スライド化で「分かった気」になりやすい
- 実は難しい側
- 相手は複雑系:因果が揺らぐ中で仮説→試行→学習が必要
- 戦略の核(診断/指針/一貫行動)が揃ってはじめて機能
- 実行の摩擦(調整・予算・現場伝達)で価値が目減りしがち

対比表①:フレームが「くれる/くれない」
| フレームがくれる | フレームがくれない |
|---|---|
| 語彙と観点のチェックリスト | 事業特有の真のボトルネック診断 |
| 整理された図と共通言語 | どこに集中し、何を捨てるかの決断 |
| 議論の土台 | 資源配分の痛みを伴う一貫行動 |
| 初学者の入口 | 現場を動かす実行の仕組み(OS) |
対比表②:良い戦略の「核」 vs よくある失敗
| 良い戦略の「核」 | よくある失敗 |
|---|---|
| 診断:真の制約・機会の特定 | 表層の事実羅列/原因が曖昧 |
| 指針:やる/やらないの明確化 | 全部やる方針/矛盾する掛け声 |
| 一貫行動:資源配分まで落とす | スローガン止まり/優先順位が動かない |
3つのポイント:こうする vs こうしない
- 思考の型を持つ(戦略カーネル)
- こうする:診断→指針→一貫行動をA4一枚で可視化
- こうしない:スライドを増やし核が薄まる
- 小さく試して学ぶ(実験的アプローチ)
- こうする:小規模・短期間・低コストで仮説検証→学習で微修正
- こうしない:一発で当てにいき調整不能に
- 実行の仕組み(OS)を整える
- こうする:OKR/BSC/定例レビューで可視化→配分変更
- こうしない:年次計画の読み合わせで終了
トレーニング法:机上の理解 vs 現場で効く鍛え方
1) 1枚戦略メモの習慣化
- 机上:スライド多枚化で要点が散る
- 現場:A4一枚に「診断/指針/一貫行動」を固定
- 例(エネルギー企業):
- 診断:政策支援×市場成長/制約は製造コスト
- 指針:コスト低減に集中、販売網は提携活用
- 一貫行動:パイロット生産→並行でパートナー開拓→半年で事業判断
2) アウトサイドビュー+プレモーテム
- 机上:自社都合の見立てで楽観
- 現場:類似案件の実績値で外枠→事前に失敗理由を言語化
- 例:許認可遅延/資材高騰を主要リスクに設定→代替サプライヤー事前契約でショック耐性
3) KPIレビューと学習ループ
- 机上:集計だけの定例
- 現場:兆候→仮説→顧客検証→改善の週次ループ
- 例:問い合わせ増×転換率低下→顧客インタビュー→資料修正→転換率2倍
まとめ:見かけの“整い” vs 本当の“効き”
- 整い:フレームで形は作れる
- 効き:診断の深さ/明確な指針/資源を動かす一貫行動+実行OS
- 次の一歩:直近テーマを1つ選び、A4一枚の戦略カーネルを作成→チームでレビュー
配布用テンプレ(コピーして使えます)
1枚戦略メモ(戦略カーネル)
- 診断:真の課題/制約/機会は?(根拠データも一行)
- 指針:何に集中し、何をやらないか?(優先順位・非優先)
- 一貫行動:資源配分・ロードマップ・測定指標(いつ/誰が/何で測る)
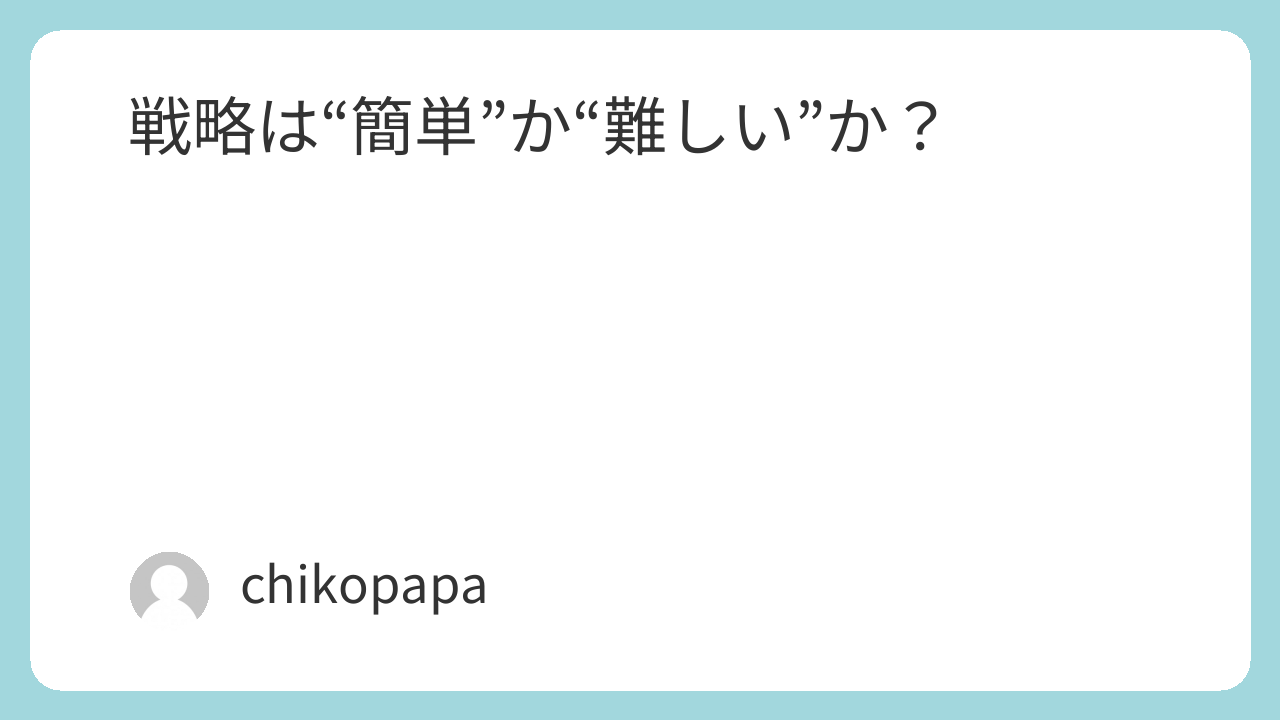
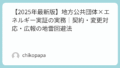
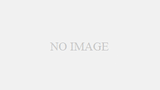
コメント