戦略はフレームで形は作れても成果を出すのは別物。本記事では、戦略が難しい本質と実行ギャップを埋める3つの鍛え方を事例付きで解説します。

「戦略なんてフレームワークを覚えれば簡単でしょ?」と思っていませんか。
確かに、形だけを作るのはそれほど難しくありません。しかし、本当に成果を生む戦略は、全く別物です。この記事では、戦略が“簡単そうに見えて実は難しい”理由と、戦略思考を鍛えるためのヒントをご紹介します。
なぜ「戦略は簡単そう」に見えるのか
戦略づくりは、一見するとハードルが低く感じられます。その理由の一つは、ポーターの5フォースやSWOT分析、ビジネスモデルキャンバスといった汎用フレームワークの存在です。これらは考え方の「型」を提供し、未経験者でも短期間で“形”だけは整った戦略案を作ることができます。
さらに、戦略の成果は数か月〜数年後に現れるため、短期的には評価が難しく、「うまくいっている」と錯覚しやすいのも特徴です。計画通りに進んでいると感じても、実際には外部環境や実行面の課題で成果が削られているケースも少なくありません。
加えて、人は自分の理解度を過大評価する傾向があります。スライド化や要約が進むほど「分かった気」になり、深い診断や現実的な検証が省略されがちです。こうした構造が、「戦略は簡単だ」という誤解を生みやすくしています。
それでも戦略が難しい本当の理由
フレームワークで形を作ることは容易でも、実際に成果を生む戦略を設計するのは別物です。最大の理由は、戦略が多くの場合「複雑系の課題」を扱うからです。因果関係がはっきりしない中で、仮説を立て、小さく試し、結果を観測しながら軌道修正する——そんな不確実な意思決定が求められます。
さらに、良い戦略の核は「診断」「指針」「一貫行動」の三要素が揃って初めて成立します。真のボトルネックを見極め、何に集中し何をやらないかを明確にし、その方針に沿って資源を配分する。この一貫性が崩れると、戦略は単なる“やりたいことリスト”に堕してしまいます。
加えて、多くの戦略は実行段階で価値を失います。社内調整や予算配分、日々のオペレーションに埋もれ、戦略の意図が現場に伝わらないまま形骸化するのです。実行ギャップを埋める仕組みがなければ、どんなに良さそうな戦略も机上の空論に終わってしまいます。
良い戦略を作るための3つのポイント
成果を生む戦略には、共通する3つのポイントがあります。
1. 思考の型を持つ(戦略カーネル)
「診断」「指針」「一貫行動」という戦略の核(カーネル)を1枚にまとめる習慣です。診断では真の課題や制約を特定し、指針で集中すべき方向を決め、行動で資源配分と優先順位を具体化します。この型を使うことで、曖昧なアイデアが明確な戦略案へと変わります。
2. 小さく試して学ぶ(実験的アプローチ)
複雑な環境では、最初から正解を当てに行くよりも、小規模な実験を繰り返す方が有効です。期間や予算を限定した試行で仮説を検証し、結果に基づいて戦略を微修正します。失敗コストを最小化しつつ前進できます。
3. 実行の仕組み(OS)を整える
どれだけ優れた戦略も、実行されなければ価値はゼロです。OKRやBSC、定例レビューなど、戦略を日々の行動に落とし込む仕組みをあらかじめ設計しましょう。実行状況を可視化し、必要に応じて資源配分を変えることが、戦略を生きたものにします。
戦略思考を鍛えるためのトレーニング法
戦略は一度立てれば終わりではなく、経験を積みながら精度を高めていくスキルです。ここでは日常業務の中で実践できる3つの方法と、その応用例をご紹介します。
1. 1枚戦略メモの習慣化
具体例:あるエネルギー企業では、「新規低炭素燃料事業の参入可否」をテーマに、診断では市場の成長性と政策支援を分析、指針では「製造コスト低減に集中し、販売網構築はパートナー活用」と明記。一貫行動として、まずはパイロット規模で生産し、並行して提携先を開拓。半年後に事業化判断の根拠が明確になりました。
2. アウトサイドビューとプレモーテム
具体例:再生可能エネルギーの新プロジェクトで、国内外の同規模案件の建設期間と稼働率を比較。そのうえで、プレモーテムで「許認可の遅れ」「資材価格の高騰」を主要リスクとして抽出し、代替サプライヤーと事前契約を締結。資材価格が上昇した際も計画を維持できました。
3. KPIレビューと学習ループ
具体例:新規サービスの立ち上げで、週次レビュー時に「問い合わせ件数は増えているが契約転換率が低下」という兆候を発見。顧客インタビューの結果、説明資料の内容がニーズとずれていることが判明し、改善後は転換率が2倍になりました。
まとめと次の一歩
戦略はフレームワークを学べば形を作ることはできます。しかし、成果を生む戦略は「診断の深さ」「明確な指針」「一貫した行動」、そしてそれらを実行に落とし込む仕組みが揃って初めて成立します。
多くの戦略が机上の空論に終わる理由は、実行段階で価値を失ってしまうからです。
そのギャップを埋めるためには、日常的に戦略思考を鍛える習慣が欠かせません。1枚戦略メモ、アウトサイドビューとプレモーテム、KPIレビューと学習ループ——この3つの実践は、どんな業界・職種でも応用できます。
今日からできる一歩として、まずは直近のテーマを1つ選び、診断・指針・一貫行動をA4一枚にまとめてみましょう。それをチームで共有し、意見をもらうことで、戦略思考は確実に磨かれていきます。
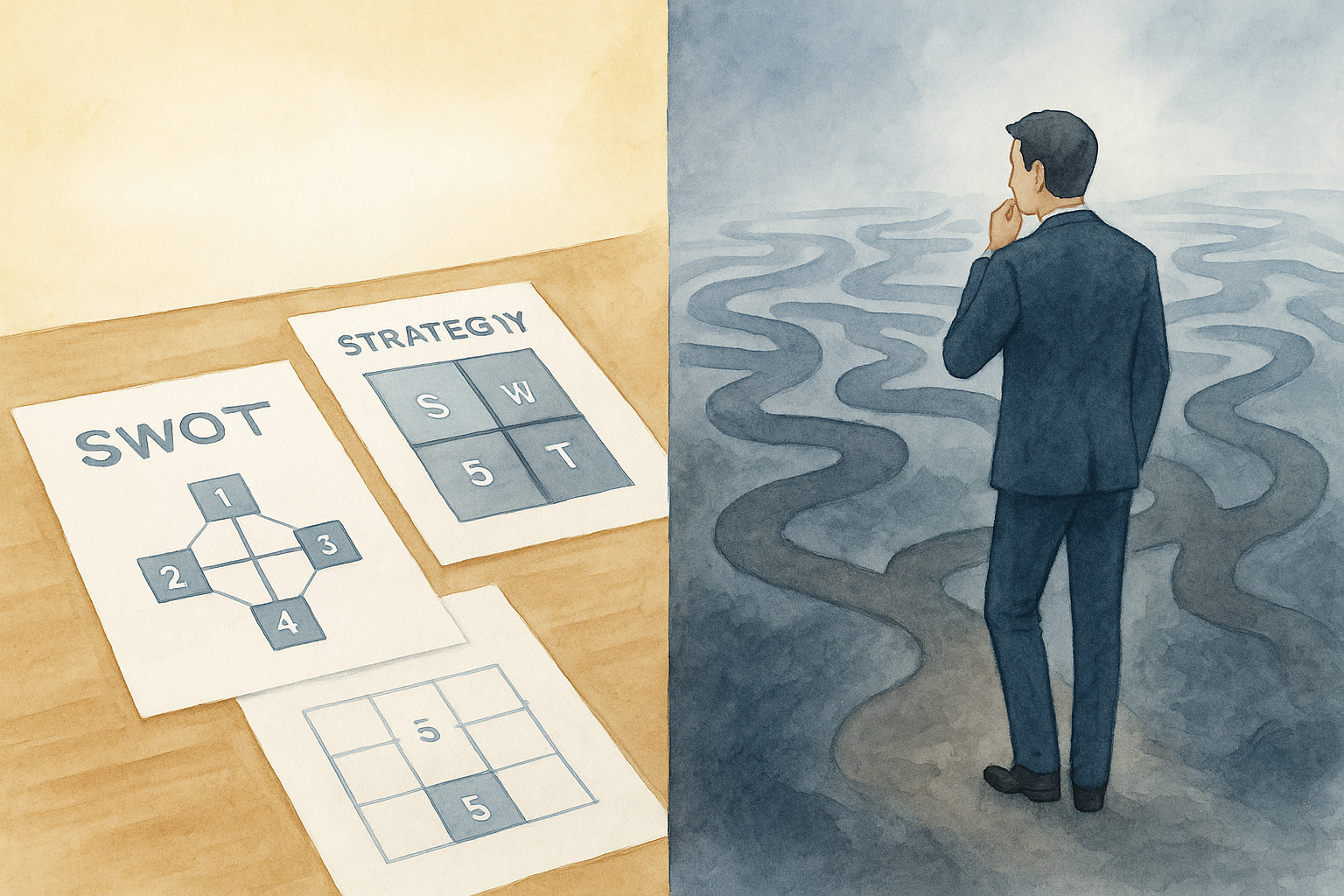
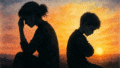
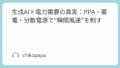
コメント