「また今日も、子供に怒鳴ってしまった…。」
布団の中でため息をつきながら、自己嫌悪に包まれる夜。
それでも明日も、同じようなやり取りを繰り返してしまう——。
もし今、その悪循環から抜け出したいと思っているなら、少しだけ立ち止まって読んでみてください。
子供が言うことを聞かないのは、あなたを困らせたいからではありません。
むしろ、その関わり方が知らず知らずのうちに、子供の「自分で考える力」を奪ってしまっていることもあるのです。
この記事では、感情的になってしまう毎日を変えるためのアドラー心理学の知恵をご紹介します。
子供の自尊心と主体性を育み、親子関係がぐっと楽になる具体的な関わり方を、一緒に見ていきましょう。
子供の問題行動、その裏にある「目的」とは?
テーブルの上に乗る。おもちゃを片付けない。スーパーで突然走り出す。
日常のあちこちで現れる“困った行動”に、つい「またわがままを!」と声を荒らげてしまうこと、ありますよね。
でも、その行動は本当に“わがまま”でしょうか?
「わがまま」の奥には必ず理由がある
アドラー心理学では、すべての行動には目的があると考えます。
子供が起こす問題行動も例外ではありません。それは「なんとか目的を達成したい」という、一生懸命なサインです。
たとえばこんな目的が隠れていることがあります。
- 注目されたい(もっとかまってほしい)
- 自分の力を試したい(「できるんだ!」と見せたい)
- 特別でありたい(自分だけを見ていてほしい)
だから、「この子はいま何を求めているんだろう?」と考えることが、対話の第一歩になります。
言葉にできないから、行動で表す
3〜5歳ごろの子供は、感情をうまく言葉にできません。
脳の前頭前野がまだ発達途中で、「お腹が空いてイライラしている」ことすら自覚できず、ただ泣き叫んでしまうこともあります。
だからこそ、親は「優しい通訳」になることが大切です。
「どうしてそうしたの?」と責めるのではなく、観察して推測し、代わりに言葉にしてあげましょう。
【具体例】お風呂イヤイヤを変える!仲間になる3ステップ
子供の目的が見えてきたら、次は「敵」ではなく「仲間」になることが重要です。
ここでは、多くの家庭で起こる「お風呂イヤイヤ(体を洗わずに湯船に入りたい)」を例に、3つのステップをご紹介します。
1. 気持ちを推察して言葉にする
「早く洗いなさい!」と言う前に、まずは推測します。
たとえば「早くお湯に入って遊びたい」という気持ちかもしれません。
親:「そっか、先にお湯に入って遊びたいんだね?」
こう伝えると、「気持ちをわかってくれた!」と子供の心の扉が開きます。
2. 共通のゴールを示す
「洗う vs 洗わない」の対立から、「楽しくお風呂に入る」という共通の目標へ切り替えます。
親:「パパも早く一緒におもちゃで遊びたいな。楽しくお風呂に入りたいって気持ちは一緒だよね!」
この瞬間、親子は「戦う相手」から「同じチーム」に変わります。
3. 部分承認+選択肢で主体性を引き出す
まず「洗いたくない」気持ちを受け止め、そのうえで選択肢を提示します。
親:「じゃあ、手だけ洗うのはどう?」
子:「…うん」
親:「いいね!次は足だけ洗ってみようか?」
小さな「YES」を積み重ねることで、自分から「全部洗ってもいいよ」という気持ちが生まれます。
失敗してもOK
毎日うまくいくとは限りません。眠い日、空腹の日、ただ「イヤ!」な日もあります。
大切なのは完璧さではなく、味方でい続けることです。
「うまくやる」よりも「気持ちをわかろうとしているよ」というメッセージが、子供に安心感を与えます。
その安心感が「自尊心」の土台になります。
自尊心がすべての土台になる理由
自尊心とは、「自分はありのままで大丈夫」と思える感覚。
これがある子は、失敗を恐れず挑戦できます。
逆に、頭ごなしに叱られる日々は、「どうせ自分なんて…」という思いを植え付けてしまいます。
危険や人を傷つける行動以外は、まず受け止める関わり方が、自尊心を守ります。
自尊心が育む一生モノの主体性
自尊心があると——
- 「やってみよう!」と行動できる
- 失敗しても立ち直れる
- 学びを次につなげられる
この循環は「幸せサイクル」と呼べるもので、親が細かく指示しなくても、子供は自ら成長していきます。
親が贈れる最高のギフト:「賢さ」と「優しさ」
自尊心の土台があれば、子供は自然に2つの宝物を手にします。
- 賢さ:自分の感情や状況を俯瞰し、柔軟に対応できる力
- 優しさ:人の気持ちを想像し、信じて関わる力
これはテストの点数では測れない、人生を豊かにするスキルです。
今日からできる一歩
完璧でなくていい。忙しい日でも、まずは1つの質問から始めましょう。
「どうしてそうしたいの?」
そのまなざしこそが、子供の未来を変える最高の贈り物になります。

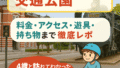

コメント