導入
地方公共団体と組むエネルギー実証って、やってみると“地雷”の宝庫です。
契約の壁、予算のズレ、住民説明…正直、甘く見ていると痛い目にあいます。
私は民間から地方公共団体に数年間出向したことがあるので、両方の立場の経験があります。それから見える成功率を上げるカギはこの3つ。
- 契約で守る
- 数字で決める
- 先に説明する
これをセットで回すと、本当に違います。
私は実際に自治体とプロジェクトを走らせて、価格交渉や契約変更、装置設計の会議まで泥くさくやりました(一次体験)。
地方公共団体と民間事業の二つの正義と衝突点
(著者見立て)お互い「正しい」ことを言ってるのに衝突するのはよくあること。
自治体は手続の正義[1]、民間は成果の正義。
だからこそ、最初に「どこでぶつかりそうか」を紙1枚に見える化しておくのがおすすめです。
目的→成果指標→手続の制約→リスク分担→広報案…これを全部1枚にまとめて“共通の地図”を作るイメージです。
スライド条項と変更契約で予算増額に対応する三段構え
(著者見立て)やり方はシンプルで、
- コストの原因を「材料/人件費/外注/物流」に分解
- 代替案を探す(VE)
- スライド条項や変更契約で正式に価格を変える
※スライド条項は発注者ごとにルールが違うので、国や自治体の要領・通達を必ず確認[2][3]。
ちなみに国交省直轄では「単品スライド」で対象工事費の1%超は発注者が負担する運用例もあります[4]。
契約変更に強くするための5条項
(著者見立て)最初の契約段階で、変更に強いかどうかが超重要。
押さえておきたいのは…
- 変更条項(スライド条項含む)
- 検収基準(性能の測り方)[5]
- 支払条件(マイルストン払い/出来高払い)
- 知財やデータの帰属
- 遅延時の責任と救済策
この辺を契約ドラフトに書き込んでおくと、あとで揉めにくいです。
装置設計会議を成功させる作法
(著者見立て)仕様は“測れるレベル”まで細かく落とすのがコツ。
「こういう機能が欲しい」→「どうやって計測するか」→「試運転」→「検収」という一直線の流れを作ります。
会議ではMUST/WANT/NOTを整理した要件表と、FAT/SATのチェックリストを準備。
議事録は「決定/未決/宿題/担当/期限」の5列に分けると後で困りません。
公務員の制度的制約と多忙さを踏まえた段取り
(著者見立て)自治体側はとにかく忙しいです。
決裁ルートは長いし、広報や議会対応までこなしています[6]。
だから締め切りは1週間前倒しで設定し、起案文や想定問答のひな形を渡すと負担を減らせます。
住民説明会・議会対応の想定問答と広報戦略
(著者見立て)突発質問は事前につぶす。
環境・安全・費用・公平性の4ジャンルでFAQを作っておくと、どんな質問にもすぐ答えられます。
(豆知識)パブリック・コメントは国は行手法、地方はそれぞれ条例で運用されています[7]。
公共案件の旅費・交通制約下での現場対応
(著者見立て)現場は大事。でも規程も大事。
タクシーは「公共交通機関が使えない/効率が悪い+上司の事前承認+区間入り領収書」が条件という運用が多いです[8][9][10]。
訪問日をまとめたり、動線を事前に決めておくと、旅費も手間も節約できます。
創業者精神で穴を埋め続ける
(著者見立て)肩書きより役割。
仕様・契約・会計・広報…穴を見つけたら、自分が埋めるくらいの気持ちで動く。
週次レビューで「決裁・契約・技術・広報」の4象限をチェックするのがおすすめです。
KPIダッシュボードで進捗と意思決定を見える化
(著者見立て)KPIは「意思決定に使えるか」で選ぶ。
おすすめは、回収年数、稼働率、円/kWh、円/Nm³(H₂)、時間一致率、契約変更件数、承認リードタイム。
毎週、閾値→アラート→是正のループを回します。
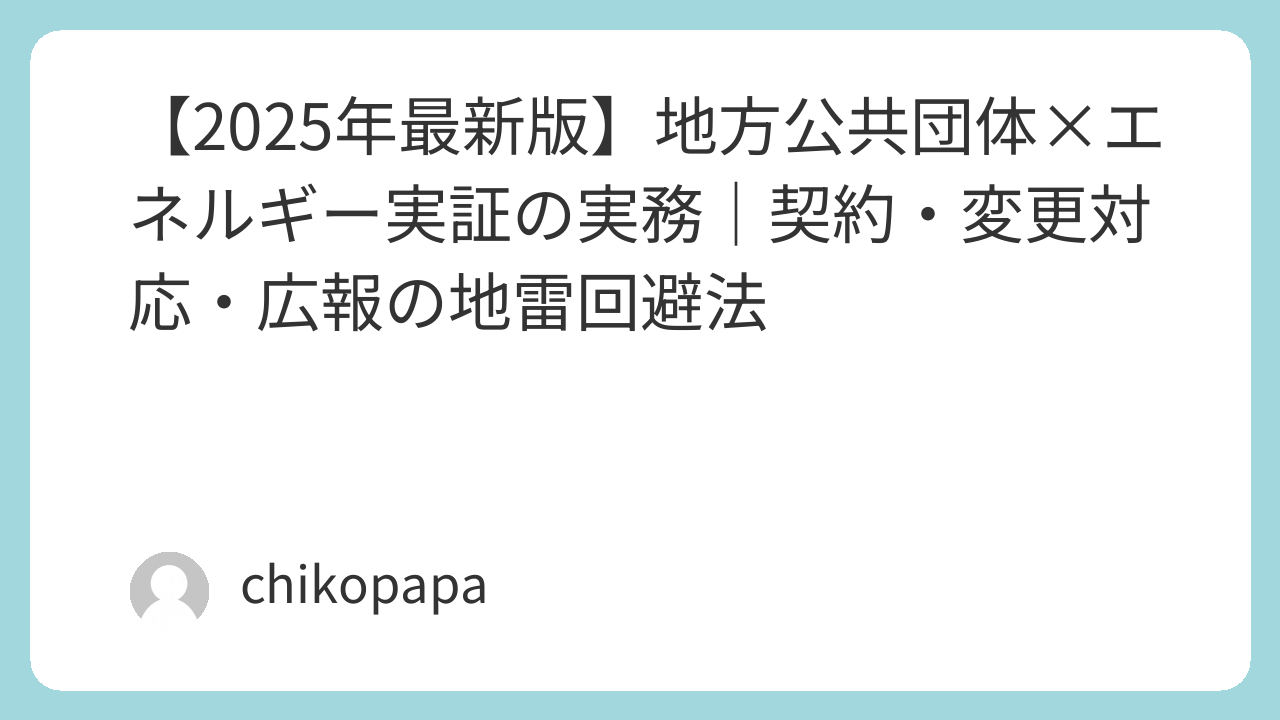
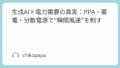
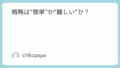
コメント